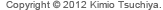REVIEWレビュー
新しい価値を見出すために新しい旅へ…
花粉と黄砂が舞う3月初旬の暖かい日、千葉県柏市郊外の自然に囲まれたアトリエに、土屋公雄さんをお訪ねしました。ご自身や作品についてはもちろんのこと、埼玉県立近代美術館で7月から企画展を予定している倉俣史朗さんとの交流についてもお話を伺いました。(小宮・金川)
父の思い出

未現像の記憶僕の父は、福井で時計の修理や卸業をしていたのですが、一年に何度か東京へ仕入れに行くことがあって、僕も小学校3~4年の頃からかな、時々荷物持ちで父にくっついて行ったのです。直江津まわりの夜行に乗って、朝、上野に着くと、最初は仕事関係の知人宅に預けられていたのですが、そのうち「お前は絵が好きだし」ということで、父は僕を上野の美術館に朝連れて行き、夕方閉館前に迎えに来てくれるようになりました。その時、館内のレストランで昼食に食べるハヤシライス代をくれてね。父も僕が美術館にいれば安心して仕事ができるし、当時福井には美術館などありませんから、僕にとって美術館は超日常で刺激的な空間に思え、半日いても飽きなかったことを覚えています。
僕が美術に進むことについて、父はあまり賛成してくれませんでした。大学は建築デザインの方へ進んだので「それならいいだろう」と言ってくれたのですが、結局僕は建築には進まず美術の方へシフトしてしまったものだから、その頃の僕と父は些細な事でぶっかっていましたね。大学を卒業しても定職には付かず、親父としてはずいぶん心配だったでしょう。息子が本当に美術の世界で生きていけるのか、最後まで心配していましたね。
漱石の言葉
学生時代に読んだ夏目漱石の中に「一番悲しい人間とは、所在のない人間である」という言葉があります。漱石が言っている「所在」とは、単なる住処としての場所ではなくて、人間の心の奥に内在した場所、言いかえればアイデンティティのようなものだと思うのですが、「いったい自分にとっての所在とは何だろう?」「自分とは何だろう?」、「はたして自分がやろうとしている建築で、この問題の答えを出せるのだろうか?」ということを、当時はいつも考えていましたね。とにかく漱石は僕にとって、「所在」「自我」について疑問を抱かせた存在でした。漱石って、国民的作家として広く読まれてきましたが、決して立派な「青雲の志」のようなものを書いた作家ではなくて、文明をシニカルに見つめながら、文明が進めば進むほど人間は孤独になり、救われがたくなっていくことを案じていたのでしょう。彼の小説のほとんどは自我の問題であり、時代の本質を見つめながら人間の内面世界を描いています。
僕が生まれた1955年前後は敗戦後の復興期であり、学生時代もアメリカの合理主義の影響を受け大量生産・大量消費・大量廃棄、まさに高度成長期にどっぷりつかり、オリンピックだ、高速道路だ、新幹線だ、高層ビルだって右肩上がりに成長していた時代です。確かに物は豊かになり生活は便利になっていくのですが、「それで本当に幸せなのだろうか?」という疑問が僕の中にあって、いつも自分は不安な気持ちから探し物をしているような微熱状態で、常に心の中に喪失感を抱えていました。それは、さっき言った「所在」の問題とも繋がっていくのですが、「この喪失感・不在感とは何か?」この疑問に対して考えてみたい。「制作を通して自分の生きている時代、自分自身を見つめてみたい」というのが、僕が作品を作る上で一番大きな動機になったのは間違いないですね。
流木から廃材へ、そして…

虚構もともと僕の使う流木は、自然の摂理で打ち上げられたようなモノではなく、すべて人間が一度使って捨てたモノ、現代社会が大量に排出したモノなのです。森の中の木が伐り倒され、製材されて建築材になって時間が経って捨てられていく・・・。当時はそういう流木がたくさん東京湾に打ち上げられていました。それを拾い集めて作品にしました。それが廃材になっていくのは・・・、昭和50年代以降の建売の家は、テレビや冷蔵庫の電化製品のように、簡単に廃棄されてしまうものと等価値になってしまっていたからです。僕が家の廃材で作品を作り始めた頃は、戦後の建売がどんどん解体されていく時期で、またそれは家族関係が崩壊していった時期でもあり、外側が簡単に壊れるということは内側も同様に崩壊していくのかと思えたのです。その問題は漱石の「所在」の問題に繋がっていて、「いったい僕たちは、何処へ向かっているのだろう?」「何を目指しているの?」「帰るところは本当にあるのだろうか?」「所在って何なんだ?」などと自問自答しながら、解体されていく家の廃材を使って作品を制作していたのです。
家というのは僕にとって家族の記憶装置なのです。さらに人間的な時間や出来事が織り込まれた複合的なテキストなのです。解体される前の家に入っていくと、その家に住んでいた人の痕跡を辿ると同時に、自分の中の記憶がよみがえってくる。引き出しの中の樟脳のにおいをかいだりすると、子供の頃、入学式に母親が来ていた着物の柄を思い出したりね。そんな時、僕の中では記憶と所在が繋がっていくような気がするのです。特に家は人の記憶が充満した装置であり人間存在の証です。だからそれを素材にするということは僕にとってとても重要なことなのです。記憶とは過去のものでありながら、過去のものではない。記憶は自己の身体、言い換えるなら僕の感覚や感情と深くかかわりながら、現在の自分との関係性において生成される創造的な生き物であり、僕自身の存在証明ともなるのです。

灰のバラある時、「廃材の先には何があるのだろう?」と思って焼尽してみました。廃材を繰り返し焼くと、炭として残った灰もすべて真っ白になるのです。地球上の生命はすべて、いずれこの白に戻ることも知りました。一時期、灰のインスタレーションもずいぶん制作したのですが、みんなはそれを見て終末論的だとか悲観的だとか・・・。でも僕の中では、灰を使うことは悲観的なことではなく、花咲かじいさんの話みたいに、それは単なる終末ではなく、次に生まれ変わる生の象徴だった。つまり灰(死)を生命の始まりとして捉えたかったのです。そういう思いから僕は灰を使っていたのですが・・・。
倉俣史朗さんのこと
彼と出会ったのは僕が大学三年の時です。当時非常勤をされていた黒川雅之さんの紹介で、約3か月間特別講師として来てくれました。最初の講義で建築デザインの話はほとんどされず、彼の子供の頃の記憶を、独特な口調で静かに淡々としゃべる。詩を聞いているような感覚で、初めてお会いした方なのに、僕はたちまち倉俣ワールドのとりこになってしまいました。
 彼は57歳で亡くなられましたが、それまでの約15年間お付き合いさせて頂いて、僕が次第に美術へシフトしていったのは、彼の影響が大きかったと思います。彼の作品のどれが一番好きかと聞かれると、『ビギン・ザ・ビギン』ですね。タイトルも素敵でしょ。スタンダードジャズの「ビギンを始めよう」という曲ですが、「さあ、新しいことを始めようよ」という意味にも取れるでしょ。これは著名なデザイナー、ヨセフ・ホフマンのオリジナルの椅子にステンレスの紐を巻いて内側の木製部分を燃やしてしまった作品です。彼はあえて尊敬するホフマンの椅子を抜け殻にすることで、新たな時代に向け、自己を開放し新たな表現を追及しようとしたのです。僕たちもいろんなアーティストの影響を受けながら、彼らを超えていく使命があるわけで、それは冒険的で革新的で、常に挑戦しながらそれまでの既成の考えを壊していく、壊しながら新たな創造に繋げていく・・・。当時20代の若者だった僕にとって、倉俣さんは実に刺激的で前衛な存在でしたね。あの時代は従来の既成制度を見直していこうという時代で、倉俣さんはその先端を走っていた方でした。
彼は57歳で亡くなられましたが、それまでの約15年間お付き合いさせて頂いて、僕が次第に美術へシフトしていったのは、彼の影響が大きかったと思います。彼の作品のどれが一番好きかと聞かれると、『ビギン・ザ・ビギン』ですね。タイトルも素敵でしょ。スタンダードジャズの「ビギンを始めよう」という曲ですが、「さあ、新しいことを始めようよ」という意味にも取れるでしょ。これは著名なデザイナー、ヨセフ・ホフマンのオリジナルの椅子にステンレスの紐を巻いて内側の木製部分を燃やしてしまった作品です。彼はあえて尊敬するホフマンの椅子を抜け殻にすることで、新たな時代に向け、自己を開放し新たな表現を追及しようとしたのです。僕たちもいろんなアーティストの影響を受けながら、彼らを超えていく使命があるわけで、それは冒険的で革新的で、常に挑戦しながらそれまでの既成の考えを壊していく、壊しながら新たな創造に繋げていく・・・。当時20代の若者だった僕にとって、倉俣さんは実に刺激的で前衛な存在でしたね。あの時代は従来の既成制度を見直していこうという時代で、倉俣さんはその先端を走っていた方でした。
倉俣さんの作品素材はガラスだったり金属・プラスチックだったり、一見すると冷たい感じがするのだけど、実はその逆で。彼は人間を常に意識して、人間のための空間を作っていった。作品それぞれの細部を見ると彼のぬくもりは伝わってくるのです。しかも重力を感じさせない浮遊性、無機的に見える中に彼独自の感覚や感情がたっぷり入っている。彼が工業製品に魔法の粉をかけると有機体のように生命を持つのです。そういう意味でも、彼はデザイナーというよりアーティストだと思っています。とにかく好奇心が強く創造的で、深いヒューマニティーを持った方でした。ある日僕が、「今後、美術をやろうと思っています」と言ったら、倉俣さんはニコニコしながら「ワインで乾杯しよう」と言って下さったのが、昨日のことのようです。
学生たちへのメッセージ
アーティストには3つの壁が立ちはだかります。一つ目は経済の壁。二つ目はオリジナリティの壁。いろんな人から影響を受けていくのですが、いずれはそれを超え自分独自の世界を作っていかなくちゃいけない。三つ目は孤独の壁。作家は常に一人で戦うのです。今の世界は、バーチャルなイメージが現実を覆いつくし、美術はサブカルチャー化し、日常の中にとろけ出してしまっている。美術もかつてのような規範が我々を支えてくれるわけではありません。新しい価値を見出すためにも、自己の内面を見つめながら新しい旅に出るしかないのです。かなり苦しいことだと思うのですが、しかしこの苦しい時代とも正面で向き合うこと、直視することが必要だと思うのです。情報は大量に入ってくる、情報の洪水におぼれない為にも、何が自分にとって一番大切なものかを見極める為にも、世界を水平に見るのでは無く、自分の足元をきちんと見据え個々を垂直的に見ることが大切だと思います。
ファムス・インタビュー 掲載記事