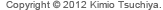REVIEWレビュー
アートと建築のつながる場所
「所在」についての問い
 大学では建築デザインを勉強しました。卒業後自分が建築の方に行くべきか確信がなかったので、少し時間をとって考えてみたいと思いました。若い頃はこの後どうやって生きていくのか、なかなか見えない。その時期に夏目漱石に出会いました。漱石の「倫敦塔」という作品に、「凡そ世の中に何が苦しいと云って所在のない程の苦しみはない。」という文章があります。所在とはいわゆる在所(ざいしょ)という物理的な場所を指すものではなく、人間の内側の帰るところ、つまりアイデンティティというものに繋がりますが、それを持てない人間は一番悲しいのだ、というように私は解釈します。旅に出るのが好きで、アルバイトしながらお金を貯めて、学生時代から外国に出かけていました。向こうの人たちに「国籍はどこ?」と聞かれ、何も考えずに「私は日本人です」と答えていました。そのうち本当に日本とは自分にとって何だろうということを異国で考えるようになり、漱石の「所在」の問題も含めて、「自分はいったい誰なのか」という問いかけがどんどん膨らんでいったのです。私は基本的にアートに興味があり見てはいましたが、現代美術をきちんとアカデミックに学んでいなかったので最初はよくその表現の意味が分かりませんでした。しかし眼の前に広がっているものは理解できないのですが、ギャラリーや美術館の空間がとても気持ちよく感じられました。そのうち何故作家はこういう作品を造るのか、その背景が知りたくなって現代美術を学ぶようになりました。美術を通して「自分とはいったい誰なのか」を問うこと、美術というものがそういった問いへの媒体になっていることを理解するようになり、更に美術に傾倒して行きました。倉俣史朗さんとは、学校でお会いしてから、亡くなるまでお付き合いさせていただきました。倉俣さんの事務所に行くと、「君は建築やデザインの世界じゃないね。アートの世界ってこういう世界だよ」という話をしていただきました。事務所にはデザインよりもアートの本が多く、僕は倉俣さんの蔵書を見せてもらいヨーゼフ・ボイスやアルテ・ポーヴェラを知ったし、田中信太郎など現代アーティストとも出会ったのです。
大学では建築デザインを勉強しました。卒業後自分が建築の方に行くべきか確信がなかったので、少し時間をとって考えてみたいと思いました。若い頃はこの後どうやって生きていくのか、なかなか見えない。その時期に夏目漱石に出会いました。漱石の「倫敦塔」という作品に、「凡そ世の中に何が苦しいと云って所在のない程の苦しみはない。」という文章があります。所在とはいわゆる在所(ざいしょ)という物理的な場所を指すものではなく、人間の内側の帰るところ、つまりアイデンティティというものに繋がりますが、それを持てない人間は一番悲しいのだ、というように私は解釈します。旅に出るのが好きで、アルバイトしながらお金を貯めて、学生時代から外国に出かけていました。向こうの人たちに「国籍はどこ?」と聞かれ、何も考えずに「私は日本人です」と答えていました。そのうち本当に日本とは自分にとって何だろうということを異国で考えるようになり、漱石の「所在」の問題も含めて、「自分はいったい誰なのか」という問いかけがどんどん膨らんでいったのです。私は基本的にアートに興味があり見てはいましたが、現代美術をきちんとアカデミックに学んでいなかったので最初はよくその表現の意味が分かりませんでした。しかし眼の前に広がっているものは理解できないのですが、ギャラリーや美術館の空間がとても気持ちよく感じられました。そのうち何故作家はこういう作品を造るのか、その背景が知りたくなって現代美術を学ぶようになりました。美術を通して「自分とはいったい誰なのか」を問うこと、美術というものがそういった問いへの媒体になっていることを理解するようになり、更に美術に傾倒して行きました。倉俣史朗さんとは、学校でお会いしてから、亡くなるまでお付き合いさせていただきました。倉俣さんの事務所に行くと、「君は建築やデザインの世界じゃないね。アートの世界ってこういう世界だよ」という話をしていただきました。事務所にはデザインよりもアートの本が多く、僕は倉俣さんの蔵書を見せてもらいヨーゼフ・ボイスやアルテ・ポーヴェラを知ったし、田中信太郎など現代アーティストとも出会ったのです。
 そんな中ぜひ外国で勉強してみたいと思い、30歳を過ぎてからロンドン芸術大学大学院のチェルシー・アート・カレッジに進みました。印象的だった授業で、「毎日必ず1点作品を完成させなさい」という課題がありました。前の日に作った作品を次の日に継続して展開させてはいけない、まったく別の新しいものを作るという条件つきで、約40日間の制作でした。最初の一週間は自分のポケットからいろんなアイディアが出てくるのですが、10日もたつともう出て来なくなるのです。それでもなんとか絞り出す。一日24時間ずっと作品のことを考えているようになります。最後に自分の前に全部の作品を並べるのですが、約40点の作品を客観的に俯瞰すると、自分では全く別個の作品を作ったと思っていたものの中に、ある共通項が見えてくるのです。まさに自分の中の自分というものを映し出す鏡のように自己に知らしめた貴重な経験でした。近代の日本彫刻というのはどこか西洋から入って来たものの亜流として捉えられていた感がありましたが、80年代に入り日本の経済が力を増すにつれ、日本の現代美術も海外から注目をされるようになりました。僕は非常にラッキーだったのですが、アメリカで初めての日本の現代美術展として巡回した「プライマル・スピリット」という展覧会にノミネートされて、川俣正、戸谷成雄、遠藤利克等のアーティストたちと共に巡回することができました。それから様々な展覧会から声がかかるようになり、30代はほとんど海外を拠点に作家活動をしてきました。90年代に入って、今でいうと環境彫刻ということになるのでしょうか、美術館の外で制作にするようになっていきました。90年代は美術館からアートが出て行く時代、つまり一部の美術愛好家が建物の中で作品と向き合っている状況が変化して、アートや演劇などが地域の中に入っていった時代です。従来の野外彫刻というとオキモノ彫刻というか、ここに存在する必然性がどこにあるの?という作品が多く、僕はずっと疑問を持ってきました。場所と彫刻との関係がこんな希薄でいいのか。彫刻と場所の関係性、あるいは地域や歴史・風土との関係性といったこと、自分が作品をつくる場合には「そこでしか成立しないもの」「その場所に深く根ざしたもの」を創っていきたいと思いました。場と向き合いながら作品を創っていくというのは、ある意味で建築と結びつくことであり、僕の中では、建築とアートというものがもっと融合したかたちで関係を持てないかと考えてきました。
そんな中ぜひ外国で勉強してみたいと思い、30歳を過ぎてからロンドン芸術大学大学院のチェルシー・アート・カレッジに進みました。印象的だった授業で、「毎日必ず1点作品を完成させなさい」という課題がありました。前の日に作った作品を次の日に継続して展開させてはいけない、まったく別の新しいものを作るという条件つきで、約40日間の制作でした。最初の一週間は自分のポケットからいろんなアイディアが出てくるのですが、10日もたつともう出て来なくなるのです。それでもなんとか絞り出す。一日24時間ずっと作品のことを考えているようになります。最後に自分の前に全部の作品を並べるのですが、約40点の作品を客観的に俯瞰すると、自分では全く別個の作品を作ったと思っていたものの中に、ある共通項が見えてくるのです。まさに自分の中の自分というものを映し出す鏡のように自己に知らしめた貴重な経験でした。近代の日本彫刻というのはどこか西洋から入って来たものの亜流として捉えられていた感がありましたが、80年代に入り日本の経済が力を増すにつれ、日本の現代美術も海外から注目をされるようになりました。僕は非常にラッキーだったのですが、アメリカで初めての日本の現代美術展として巡回した「プライマル・スピリット」という展覧会にノミネートされて、川俣正、戸谷成雄、遠藤利克等のアーティストたちと共に巡回することができました。それから様々な展覧会から声がかかるようになり、30代はほとんど海外を拠点に作家活動をしてきました。90年代に入って、今でいうと環境彫刻ということになるのでしょうか、美術館の外で制作にするようになっていきました。90年代は美術館からアートが出て行く時代、つまり一部の美術愛好家が建物の中で作品と向き合っている状況が変化して、アートや演劇などが地域の中に入っていった時代です。従来の野外彫刻というとオキモノ彫刻というか、ここに存在する必然性がどこにあるの?という作品が多く、僕はずっと疑問を持ってきました。場所と彫刻との関係がこんな希薄でいいのか。彫刻と場所の関係性、あるいは地域や歴史・風土との関係性といったこと、自分が作品をつくる場合には「そこでしか成立しないもの」「その場所に深く根ざしたもの」を創っていきたいと思いました。場と向き合いながら作品を創っていくというのは、ある意味で建築と結びつくことであり、僕の中では、建築とアートというものがもっと融合したかたちで関係を持てないかと考えてきました。
リバー・プロジェクト
 この春3月に、チェルシー・アート・カレッジと武蔵野美術大学の合同ワークショップを開催しました。このプロジェクトは3年前から考えていたのです。今までの国際交流は、学生個人が交流のある大学に留学し、1年間滞在して帰ってくるといった個人べースのもので、本人しか海外で学べないという事が閉鎖的だと思いました。もっと開かれたかたち、例えばゼミ単位で大学の授業に参加できないかと考えました。僕自身も海外の大学で学び、芸術という目標に向かって世界各国から来た人間と切磋琢磨し、お互いの文化や考え方の違いについてディスカッションし、価値観の違いといったものを認め合う事を学びました。武蔵美の学生たちにもぜひそういう体験を持ってもらいたいと思いました。2006年に武蔵野美術大学とロンドン芸術大学が国際交流協定締結校という運びになり、チェルシー・アート・カレッジのヘッドも日本に来られ、国際交流ワークショップの企画を膨らませました。まず最初は日本からイギリスに行くことになりました。武蔵美は学部生、大学院生と卒業生で計11名、そして高橋晶子先生、研究室の西尾さんと僕というメンバーで渡英しました。チェルシーはスペース・デザインのコ-スの学科長であるケン・ワイルダー氏と大学院の25名の学生に参加してもらい、総勢36名の学生によるワークショプとなりました。テーマを考えるにあたっては、お互い先進国ではありますが、地域毎に背景も違い、共有事項という点では神経を使いました。世界の主要都市の真ん中には大きな川が流れていますが、ロンドンではテムズ川、東京では隅田川ということで、テムズ川と隅田川を対象に、「川」というものをキーワードにしてプロジェクトを進めようという事になりました。
この春3月に、チェルシー・アート・カレッジと武蔵野美術大学の合同ワークショップを開催しました。このプロジェクトは3年前から考えていたのです。今までの国際交流は、学生個人が交流のある大学に留学し、1年間滞在して帰ってくるといった個人べースのもので、本人しか海外で学べないという事が閉鎖的だと思いました。もっと開かれたかたち、例えばゼミ単位で大学の授業に参加できないかと考えました。僕自身も海外の大学で学び、芸術という目標に向かって世界各国から来た人間と切磋琢磨し、お互いの文化や考え方の違いについてディスカッションし、価値観の違いといったものを認め合う事を学びました。武蔵美の学生たちにもぜひそういう体験を持ってもらいたいと思いました。2006年に武蔵野美術大学とロンドン芸術大学が国際交流協定締結校という運びになり、チェルシー・アート・カレッジのヘッドも日本に来られ、国際交流ワークショップの企画を膨らませました。まず最初は日本からイギリスに行くことになりました。武蔵美は学部生、大学院生と卒業生で計11名、そして高橋晶子先生、研究室の西尾さんと僕というメンバーで渡英しました。チェルシーはスペース・デザインのコ-スの学科長であるケン・ワイルダー氏と大学院の25名の学生に参加してもらい、総勢36名の学生によるワークショプとなりました。テーマを考えるにあたっては、お互い先進国ではありますが、地域毎に背景も違い、共有事項という点では神経を使いました。世界の主要都市の真ん中には大きな川が流れていますが、ロンドンではテムズ川、東京では隅田川ということで、テムズ川と隅田川を対象に、「川」というものをキーワードにしてプロジェクトを進めようという事になりました。
ロンドンの学生たちは世界各国から来ていて、25人中イギリス人は3人しかいないという正にインターナショナルな状況で、そこに日本人が入っていっても全然違和感がなく、我々もチェルシーの学生になってしまうような感覚でした。事前に武蔵美の学生は隅田川のリサーチをして、江戸時代まで遡って、東京とはどういう街であり、国際都市になるまでどの様なプロセスを経てきたか、川が果たして来た役割について、東京オリンピックを機に高速道路が建設され街が変わっていった状況などをプレゼンテーションしました。チェルシー側は、テムズ川の歴史をケン・ワイルダー先生がレクチャーしてくださいました。そしてまず現地調査から始めました。
最初の日は船に乗ってテムズ川を下り、船からテート・モダンやミレニアム・ブリッジなど色々なものを見つつ、時々下船して調査をしていったのです。今回は36人の学生をシャッフルし、1チーム5~6名を5組作り、学生たちの自主性に委ねるかたちでチーム毎に行動させるようにしました。最初の内は全体で行動していましたが、徐々にそれぞれのチームに分かれて動き始め、夕方前にはチーム毎に教室へ戻り「何をやろうか」ということでディスカッションが始まりました。どうしても英語がわからないという人は助手の西尾さんに通訳してもらっていましたが、しばらくするとスケッチや、その他のコミュニケーション・ツールを駆使して自由にコミュニケーションを取り始めました。
2日目からは各チームでのリサーチに入りました。ロンドンでは一歩外へ出ると人種問題や貧困など、日本であまり経験しない問題も見えてきます。例えばテムズ川の南側と北側では実はある種の人種格差があり、南のほうにいくとワーキングクラスの人たちが多いという政治的状況があるのです。武蔵美の学生たちも行動していくうちに、このエリアはアラブ人が多いとかインド人が多いとか気づいていったし、様々な事実を彼ら自身が見い出せた事はよかったと思います。テムズ川には船の中で生活しているボート・ピープルたちがいますが、あるチームはそういったボート・ピープルをリサーチし、実際にボートに入り話を聞き、そこでの生活を学びました。東京では想像し得ない文化・歴史・政治の違いを体感したと思います。短期間でしたが、濃厚に凝縮された時間のなかで成果を出したと思います。僕のゼミの卒業生である越後君がチェルシーの研究生であり、大変力になって くれました。
制作中は日本の学生がリーダーシップをとっていく姿も見られました。制作だけでなく、武蔵美の学生たちが英語でプレゼンテーションする原稿を一生懸命現地の学生と相談しながらつくっていました。自分の言葉で発表する彼らの勇気というものは本当に嬉しかったです。この経験で学生たちは自分の力を確信できたし、大きな自信になったと思います。 同時に自分自身に不足しているものも自覚する機会になったと思います。向こうの学生は手がよく動き、のんびりと構えて考えているよりも手と頭の中間でイメージしていくというプロセスを体得しています。そのことを武蔵美の学生たちにも気づいてもらえました。
価値観が多様化している時代に
今度僕はニューヨークに行こうと思っています。マンハッタンのハドソン川沿いにハイラインという運送用の鉄道が走っていた高架橋があります。1920年代につくられたもので、鉄道が車に取って代わってから使われなくなって、放置され草ぼうぼうになっています。2002年にこの高架橋を壊して跡地を経済的に活用しようということになりました。しかし地域の人たちにとってハイラインはアイデンティティの一部であり、当時のデザインのしっかりした鉄骨造で、簡単に壊れるものではありません。沿線にはチェルシーのギャラリー街やアートセンターがあり、若い人や観光客たちが集まる場所になっています。
ニューヨーク市議会では取り壊すということになっていたのを、反対運動が起きて取り壊し中止となりました。デザインコンペをして、ここをどのように再生し経済効果を出して行くかということになり、パブリックスペースにする計画が通ったのです。こういった再開発プロジェクトは世界中にあり、日本の建築家やアーティストたちもこういった問題を積極的に考えていかなくてはいけないと思います。
経済効率、機能といったことばかり優先する時代にあって歴史的な建造物が壊されて来たのを、地域住民やアーティスト、デザイナーや建築家によって守られたのは素晴しい事です。価値観が多様化している時代にあって、社会における新しい価値や役割、環境やコミュニティの問題などを私達も積極的に考えていくべきです。
武蔵美の建築の学生は建築を学ぶと同時に美術も学んでいるから、領域横断的にこういったプロジェクトに関わって行くことができると思います。僕自身は建築専門ではないけれど、美術を中心におきながら領域を超えたところで建築学科に関わっていければと思っています。
若きアーティストたちへ
 「この体験なき情報化の時代は、世界を水平に見るのではなく、個々を垂直に見る座標軸が必要である」(土屋公雄ブログより)
「この体験なき情報化の時代は、世界を水平に見るのではなく、個々を垂直に見る座標軸が必要である」(土屋公雄ブログより)
毎日情報の洪水のなかに生きていると、我々は自分を見失ってしまいます。自分にとってどの情報が大切かという見極めがないと、ただ受け入れるしか無く、どんどん自分が見えなくなってしまいます。
自分の両足で立っているのだという確認の意味でも、足元を掘ってみてほしい。縦軸と横軸の交わる所に常に立っていてほしい。僕はそれが今の時代を生きるバランス感覚だと思っていますし、武蔵美の学生たちにはそれが持てると思います。
一学年80名ぐらいなので、卒業までに全員の名前は憶えられませんが、自分が関わった学生はこれからもしっかりと追っかけて行こう、見て行こうと思っています。ゼミの卒業生は一年に1回集まってくれますし、「たまには近況報告に来いよ。」と言っています。皆の将来を楽しみにしています。僕は教育という現場において、常に学生たちと実践的プロジェクトに関わっていきたいと思っています。
フォルマ・フォロ Dec.1 Vol・9 土屋公雄 インタビュー
取材編集:坂本和子、青山恭之