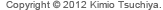REVIEWレビュー
「時間」と「存在」の意味を問う

虚構 土屋公雄の作品を見た時に自分の身体に走った衝撃は忘れることができない。 1992年、「所在」と題された個展の折に青山のスパイラルホールで展示された作品「虚構」は、ある家族が暮らした家を解体し、その解体材によって1つのオブジェ、立体作品を完成させたものだった。
土屋公雄の作品を見た時に自分の身体に走った衝撃は忘れることができない。 1992年、「所在」と題された個展の折に青山のスパイラルホールで展示された作品「虚構」は、ある家族が暮らした家を解体し、その解体材によって1つのオブジェ、立体作品を完成させたものだった。
作品を丹念に見てゆくと、解体前の家族が捨てていった家族の記憶に繋がる品物が見えてくる。例えば、少年野球のバットや家族の誰かが手にしたトロフィー、時計や電話帳、読み手の顔が浮かぶような本の数々など、昭和の雰囲気が漂う品物が解体材の中に埋め込まれている作品だった。
ひとりひとりの人間の歴史とその記憶。忘れ去られてゆく存在。そこにあった家がなくなってしまうという喪失感。リアルな生活感のある品物を使いながら、まったく別の生活感を生み出している。ノスタルジーと共に、物質文明への批判も感じられる優れたインスタレーションであった。

石造の暦土屋公雄の作品に魅せられてから、イギリスの湖水地方(ピーター・ラビットの故郷として知られる)にあるウィンダミアからすぐのグライスデールという小さな村のフォレストミュージアムに設置された作品「石造の暦」を見に行ったこともある。グライスデールフォレストは、小さい村ながら素晴らしい試みをしている森の美術館で、毎年1,2名のアーティストを招聘し、滞在中に1つの作品を仕上げてもらうのだが、その時に木や石など、天然素材を使うことを条件としており、時間の経過と共に森と立体作品が一緒になってゆくというもである。森の中にはキャプションや道順のサインなどまったくなく、観客はレンタサイクルか徒歩で自分の眼で作品を探しながら見て廻る。ストーンサークルがあったり、放牧されている羊の柵は石造りというスコットランドの古い歴史の流れを実感出来る田園風景は、土屋公雄の魂を呼んだのではないか、と思えるほどに、出会うべくして出会ったような雰囲気があった。
グライスデールフォレストの中に完成した「石造の暦」は、その地方にある断面がきれいに割れてゆく石を積み上げて作った巨大な5つの塔のような作品だったが、霧の漂うグライスデールの森の緑色と濃いグレーのの石でできたコントラストは非常に美しかったことを記憶している。「石造の暦」はこれから長い時間をかけて、この森と共に、苔むし、朽ちてゆくのである。

永劫
記憶と終わりなき創造である土屋公雄の作品を大きな枠で捉えると「時間」と「存在」という大きなテーマが見てとれる。大学で建築を専攻した彼は「建築はフィクションである」と言う。建築はその場所に流れてきた時間を一度、断ち切り、そこに新たな構築物を作るからだ。土屋公雄の作品を見る度、本人に会う度に、作品のコンセプトの純度はより高くなり、想いも強くなっているように思える。
土屋公雄を最初に評価し、コレクションしたのもやはり欧米のキュレーター達だった。特にイギリス、フランスでの評価が高く、前述のイギリスのグライスデールのほか、フランスのヴァシビエール現代美術館、カナダのモントリオール現代美術館など、存在感のある美しい彼の作品がいつでも見られる環境にある。彼の作品をコレクションするには、小作品でない限り、大きな庭か壮大な森が必要である。海外の別荘や会社の中庭も最適だ。シドニーで画廊を経営する私の友人は、2000年のシドニーオリンピックの時に、シドニー湾が見えるボタニカルガーデンに土屋公雄作品を展示し、高い評価を得た。

Mの記憶その土屋の作品がアートプロジェクトの作品として、21世紀になってポツポツと日本国内でも見られるようになった。東京近郊なら東京駅のすぐ近くの丸の内ビルディングの1階にある「Mの記憶」、東京の横網公園の東京空襲犠牲者追悼・平和モニュメント、アメリカ大使館や、ブリティッシュ・カウンシル。西日本なら、山口県宇部の常磐彫刻公園などで見られる。それでもまだ数は少ない。人々が憩う日比谷公園や代々木公園など普段、気軽に作品を目にできる場所に土屋の代表作があって良いと思う。
一昨年には活躍する彫刻家に贈られる第11回本郷新賞も受賞、現在もっとも脂が乗っている。残念ながら私には土屋作品の似合う、別荘や大きな庭がない。それゆえ、私の夢は私の死後、お墓をやってもらいたいということなのだ。彼の石の作品に抱かれて眠ることは最高の心地よさであることを死っているからだ。「不在」と「再生」を掘り下げた彼だから、断らないでくれるといいのだが。
SEVEN. vol.016 掲載記事
取材・文:山口裕美(アートプロデューサー&現代アートチアリーダー)